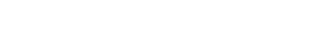ジャズ関連書籍の紹介
例えば、練習に飽きてしまったり、壁に突き当たったときは、思い切って教則本を閉じてしまいましょう。
そんなときに必要なのは、練習でも楽譜でもありません。 それは、少しばかりの「好奇心」と「知識」かもしれません。
たとえほんのわずかでも、物事を一つの方向からしか見なかった自分の存在に気が付くには充分です。 たった一つの言葉で、自分が変わり、そして世界は一瞬で変わります。
-
憂鬱と官能を教えた学校
- 菊地成孔、大谷能生(著) /河出書房新社

サブタイトルに、「バークリー・メソッドによって俯瞰される20世紀商業音楽史」って書いてなかったら、絶対に勘違いする人いるでしょうね。
いや~ほんと私としては、すご~く楽しめちゃいました。
でも、ジャズピアノを始めたばかりの私だったら、最後まで読めなかったかも。
市販の教則本の内容が半分ほどでも理解できれば、かなりオススメだと思います。
内容は、アメリカにある超有名なバークリー音楽院が音楽に対してどれだけ影響を与えたかっていうお話しです。
有名なミュージシャンって、ここ出てる人が多いんですよね。
つまり、私たちの使っている教則本ってのは、すべてこのバークリーメソッドがルーツだってことです。
学生の前での講義を起こした文章なので、話し言葉そのままなところが、とても臨場感たっぷりです。
面白くて、しかも分かりやすい。
この著者、ただ者じゃありません。
-
鍵盤を駆ける手―社会学者による現象学的ジャズ・ピアノ入門
- D.サドナウ(著)、徳丸良彦・村田幸一・ト田隆嗣(訳) /新曜社

この薄緑色をしたハードカバーの本が、当サイトを始めるひとつのキッカケになりました。
といっても、ジャズピアノの練習にものすごく役に立つとか、そんなんじゃありません。
サドナウっていう社会学者が、自分自身でジャズピアノを習得し、その過程を克明に書き記しています。
ジャズピアノといっても、主に「どのようにアドリブフレーズを作るか」ってことが中心です。
楽譜は、ほとんどありません。
そのかわり鍵盤の図と、鍵盤を押さえている手の写真がたくさんあり、それで説明をしています。
あまり、オススメとはいえないかもしれません。
しかし、私はこういった変な本が大好きです。