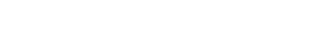23.マイナースケールの流れについて考える
私としても、ダイアトニック関連のお話しは、もうそろそろおしまいにしたいと思っています。 しかし、今回でまとめきることができるのでしょうか? というか、何とか強引にでもまとめないと先に進めません。
それより、前回までのところが完全に理解できたでしょうか? あるいは、聞き慣れないスケールがいっぱい出てきちゃってパニック寸前でしょうか? 理解できなくても、コードとは何なのか?スケールとは何なのか?なんてところが、漠然とでも分かった気になればOKです。 まあ、コードとスケールがとても深い関係だってことさえ分かればそれだけで良しといたしましょうか。
え~と、そうそう、マイナーのツーファイブワンがまだでした。 キーが、「 Cm 」なら「 Dm7b5・G7・Cm 」ってことになります。
しかし、C の平行調である「 Am 」のほうが説明し易いんですよね。 ということで、キーが Am なら・・・ こういうのが、瞬時に思い浮かばなくちゃダメです。 「5度圏」を覚えていれば、こんなものはすぐなんですけどね~
そう、「 Bm7b5・E7・Am 」です。 そして、それぞれのコードで使えると言われている一般的なスケールってのがあります。
- Bm7b5 では、ロクリアン、ロクリアン#2
- E7 では、オルタード、hmp5↓
- Am では、ナチュラルマイナー、メロディックマイナー、ハーモニックマイナー
~だそうです。
実際は、ペンタトニックやブルーノートなんてスケールも使えるのですが、それをここでやっちゃうと収拾がつかなくなりそうなのでやりません。
さて、マイナーのツーファイブワンというのは、「 IIm7b5・V7・Im 」です。
まず「 Im 」、トニックマイナーから。
この場合「 Am 」ですが、3つのマイナースケールが使えます。 というか、このマイナースケールがこのツーファイブワンの根底に流れています。 どうやらツーファイブワンってのは、大雑把にひとつのまとまりというか、ひとつの流れとして見る考え方ってのがとても大事なようです。
やはり、基本はナチュラルマイナーなのでしょうね。 だから「 IImb5 」(この場合 Bm7b5 )でロクリアンが使えるっていうのは、ものすごく納得できます。

でも、このロクリアンでは、9度のテンションが♭9になってしまい、アヴォイドノートとして使えないのでした。 で、それを少しだけ改良したのが「ロクリアン#2」(ろくりあんしゃあぷせかんど)です。
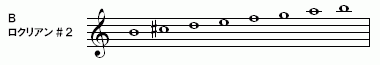
これは、ロクリアンの2番目の音を半音上げたスケールです。 これによって、9度のテンションが使えるようになりました。 というか、使いたいためにこのスケールを作ったんでしょうね。きっと。 だから、「ロクリアン・ナチュラル9」なんて言う呼び方もあるようです。 なんとも、コードの構成音としての9度(2度)を使うぞ~っていう意気込みを感じさせるようなネーミングではありませんか。 他にも、「オルタードドリアン」とかいう呼び方もあるようです。
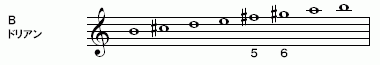
このドリアンスケールの5番目と6番目を半音下げてるっていう見方もできるからなのです。 IIm7 で使うドリアンを意識しているのかもしれません。 でも、やはり「ロクリアン#2」っていう呼び方が一般的みたいです。 そりゃそうですよね。スケールの名前なんですから、「そのスケールの2番目を半音上げた」っていう表現が最適ですよ。 このロクリアン#2は、古い教則本では載っていなかったり、呼び方がいろいろだったりするかもしれません。 よく分かりませんが、いろいろな事情があるのでしょうね。 ちなみに、この IIm7b5 は、サブドミナントマイナーってことになります。(正確には、その代理です。)
そして最後は、「 V7 」(この場合 E7 )です。
しかし、ナチュラルマイナーを基本としてしまうと、「 Vm7 」になっちゃうんですよね。 だから、V7 のようなドミナントセブンスにするには、ハーモニックマイナーかメロディックマイナーじゃないといけないのです。
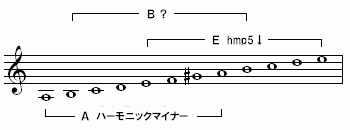
これって、メジャーのツーファイブワンでやった、C のイオニアンと G のミクソリディアンの関係とそっくりです。 多分この、hmp5↓ってスケールも最初の頃にはいろんな名前を考えたんでしょうね。 でも、結局のところ適当な良い名前がなくて、最後は面倒くさくなって、じゃあもう「5度下からのハーモニックマイナースケール」でいいじゃんってことになったのでしょう。
それから、上の図に「 B?」ってなってるところを見てください。 このロクリアンでもロクリアン#2でもない、何て名前だか分からないスケールも使えそうな気がします。 でも、m7b5 で使えるテンションに♭13があるってことは、「ソ#」ではなくて「ソ」じゃなくちゃいけないから、やはり使えないのかもしれません。 う~ん、よく分かんないけど、まあいいか~
ハーモニックマイナーは、こんなところでしょうか。
じゃあ、メロディックマイナーはどうなの?ってことです。 つまり「メロディックマイナー・パーフェクト・フィフス・ビロウ」ってのはないの?ってことです。
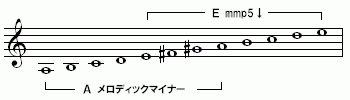
メロディックマイナーでも「 V7 」になりますからね。 多分、略せば「 mmp5↓ 」ってことになるんでしょうけど、あまり見かけません。 以前、どの教則本だか音楽雑誌の連載だか忘れてしまいましたが、実際に載っていたのを見たことはあります。 でも、メロディックマイナーを基に考えると、「 IIm7b5 」の部分が「 IIm7 」になってしまうのです。 (「ファ」の音に#が付いているところを注目)

そういた事情もあって、このツーファイブワンを同じ流れで考ようとするには、ハーモニックマイナーのほうがコード的には、自然ってことになるんでしょうね。
次に、よく言われている「マイナーキーでは、ツーファイブの V7 のテンションは♭9にする」ってのについて考えたいと思います。 あるいは、「マイナーキーでは、ツーファイブの V7 のテンションはオルタードにする」なんてのも聞いたことがあります。
どういうことかと言うと、「 E7 」って書いてあったら、テンションにナチュラル9ではなくて、♭9を加えるってことです。 あるいは、さらにもうすこし範囲を広げて、#9とか♭13も使えるってことです。
これについても教則本によっていろいろです。 「絶対にこうしなくちゃいけない」みたいに受け取れるものや、「こうすると自然です」みたいな感じや、「特にそうしなくてもいい」みたいなものなど。 それぞれの大先生たちの考え方の違いみたいなものかもしれません。 でも困ったことに、こういうところで初心者というものは迷ってしまうんです。
そうは言っても、私のような天邪鬼は、「黙ってオレの言うことだけやってりゃいいんだよ」なんて言われて、「はい、そうですか」なんて言えやしないんですけどね。 私としては、「こうすると自然です」でも「特にそうしなくてもいい」くらいの調子で考えたいんですよ。
さて、IIm7b5 の♭5って音ですが、かなりクセのある響きだと言えます。 だから、そのとても大切な♭5の音を、V7 でも受け継ごうとすると♭9になってしまうのは自然な流れなのです。
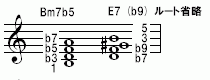
「 Bm7b5 の♭5」と「 E7 の♭9」は同じ音です。 じゃあ、E7 で#9とかナチュラル9とか使ったらどうなっちゃうんだろうってことです。 こんなもんは、ごちゃごちゃ言ってないで、実際に弾き比べてみりゃいいんです。
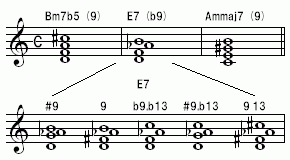
とりあえず、右手でコード、左手でルートを弾いてみましょう。 人それぞれ感じ方ってのに、多少の違いがあって当たり前です。 まあ、マイナキーってことで次の Im に行くことを考えると、より暗い♭9のほうが自然ってことなんでしょうけどね。 でもどうなんでしょうか?ナチュラル9、ナチュラル13だって、そんなに悪かぁないですよね。
マイナーのツーファイブワンの IIm7b5 を IIm7 にしちゃうってのもアリです。
つまり、「 IIm7・V7・Im 」ってことになります。 IIm7 は、♭5じゃないので、メロディックマイナーを基本にする考え方です。 IIm7 → V7 って来たときに、I へ行くのかな~って思わせといて、Im へ行って裏切る~みたいな効果があります。
さて先ほどの、マイナーのツーファイブワンでの V7 で使えるスケールですが、なんとなく(というか圧倒的に)少ないことにお気づきでしょうか。
一般的には、オルタード、hmp5↓の2つだって言われています。 どうしてでしょうか?
まあ、確かにこれ以外のドミナントセブンスのスケールでも、ミクソリディアン、リディアン7、ホールトーンなんかは明るい感じがします。 と思ったら、♭9とか#9とか入っていませんでした。 そのかわり、ナチュラル9です。 だからなんですね。きっと。 でも、使っちゃっても別に構わないのではないかと思うのです。
さて、そろそろまとめなくちゃいけません。 う~んでも、何かメジャーに比べてマイナーってのは、イマイチ理論的にスッキリしないんですよ。 多分、これらの理論を構築しようとした偉人さんたちも苦労したんでしょうね。 もともと、どうしようも出来ないものを、なんとか強引に理論づけようとしたって感じもします。 その結果が、3つのマイナースケールってことなのかもしれません。